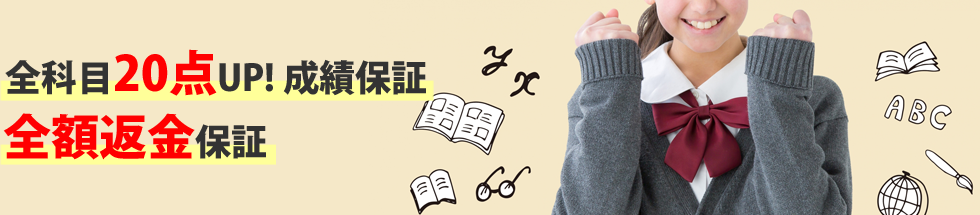頭を良くするとは?
最近、ネットの世界ではIQを上げることができると主張する人が目につきます。本来ならば、「IQを上げることが可能か」という問題に対して何らかの結論を出せると良いのですが、かなり大変なので、断念しました。ですが、多くの人がなぜ自分の子供のIQを上げたいと思うのかについて深掘りしてみましょう。IQテストの多くは、いかに速く図形の規則性を見つけられるか、という問題です。となると、IQが上がればそれが素早くできるようになるし、それが素早くできるならばIQが高いことになります。ですが、図形の規則性が速く見つけられたから嬉しいでしょうか、役に立つでしょうか。いや大して嬉しくもないし、大して役にも立ちません。もしかすると千葉県公立高校入試の数学大問4で役に立つかも知れない程度のお話です。そもそも、私たち大人が子供たちにつけてもらいたい能力は、図形の規則性を素早く発見する能力ではなく、5教科の試験で高い点数を取る能力だと思います。アラジンの魔法のランプがあるならば、図形の規則性を速く見つけられる能力よりも、5教科の能力の方を望むはずです。IQを高めたい(=IQテストのスコアを伸ばしたい)ならば、ひたすらに図形の規則性を発見する訓練を積めばできそうですが、できたからと言って、「だから何なんだ?」となるでしょう。
だったら、最初から教科の勉強や訓練を積む方がいろいろとご利益があります。というわけで、うちの塾ではIQを上げるプログラムを用意しておりません。おそらく他塾もそうでしょう。
ただ、素早く計算する訓練プログラム、素早く読解するプログラム、素早く暗記するプログラム、などの頭を良くするプログラムはできれば良いなとは思います。今のところ未完成で、断片的に運用しているだけですが。
未完成ながら、途中経過をお話しします。
<計算を速くする>
例えば、素早く計算するプログラムは、暗算が主体です。これは、九九の考え方と本質的には同じです。詳しく言えば、七を九個足すよりも「七九63」と暗唱した方が速いという考え方です。世の中には暗算を禁止している教育者もおられますが、さすがに九九を否定している人は見当たりません。どうして暗算を禁止するのに九九は例外なのでしょうか。筋が通っていないと思うのは私だけでしょうか、いや違う。おそらく、その真意は安易に暗算して間違うのを嫌ってのことでしょう。だったら、「えいや!と暗算して間違うのはダメだ。自信がなければ検算せよ」と指導すれば良いのです。それを味噌も糞も一緒にして一律暗算禁止にしてしまうと、せっかくの才能を潰してしまいかねません。一律禁止というのは大抵がものぐさの発想です。暗算をしようともせずに何でもかんでも筆算する人はせっかくの脳の訓練の機会をことごとく逸してしまっています。ああ、もったいない。私は計算の度にできるだけ暗算しようとして、結果的に暗算のトレーニングをしています。すると、少しずつ暗算が上達するのです。計算のたびに暗算を試みるので段々と上達します。かくして私の暗算能力は5年前の1.2倍ぐらいになったのではないでしょうか。だとすれば小中高生の若い頭脳ならばもっと伸びるはずです。こうした事情を踏まえて、数学を受講している生徒(全員ではありませんが)にチラッと暗算のトレーニングを勧めている次第です。
<素早く読解する>
素早く読解するためには、理解できるスピードで速く読むことなど意識しないで、ひたすらにたくさん読む。そうすると長い目で見て、自然と速く読めるようになります。それに尽きます。日本語でも英語でもそうです。自分にとって少し難しい文を読むのが良いでしょう。国語が好きな中学生ならば大学入試の現代文を読むことをお勧めします。ただし、大学入試の現代文に興味がないのなら、岩波新書、講談社現代新書、中公新書、ブルーバックスなどの新書の中から興味のあるものを選んで読むと良いでしょう。
<素早く暗記する>
素早く暗記できれば学校の勉強では格段に優位に立てます。ネットで検索すると記憶力の大会で優勝したらしい人が暗記法を披露していますが、今一つ食指が伸びません。いちいち記憶法を使って暗記してしまうと、常に記憶法を媒介にして思い出さなければならなくなってしまうからです。分かりにくいので具体例を挙げます。高校化学で炎色反応を暗記する場合の例です。Li (リチウム)は赤、Na (ナトリウム)は黄、K (カリウム)は紫です。これを暗記するのに「リアカー無きK村」と暗記するのが受験界の常識です。そうすると「カリウムの炎色反応は何色か」という問題に当たったときに、いちいち「リアカー無きK村」を思い出して、「ええと、K村だからカリウムの炎色反応は紫だ!」となってしまいます。受験では大量の暗記事項があります。それらを覚えるのにいちいち「場所法」や「語呂合わせ」のような本質的でない方法を使えるとは思えません。これらの方法の欠点は全く本質的ではないことです。カリウムと「K村」は本質的なつながりではありません。本質的でないつながりはゴミ情報です。ゴミ情報の暗記は増やしたくないので、記憶法はほどほどにとどめるべきです。別に語呂合わせを全否定はしません、使いすぎると良くないのです。結局、素早く暗記するためには日ごろからたくさん暗記するに尽きます。たくさん暗記すれば脳が鍛えられるのです。
<AI時代に暗記は不要か→いや違う>
「AIが進化する現代において、暗記中心の教育は不要である」という主張をよく見かけます。本当にそうなのでしょうか。確かに炎色反応を答える程度ならばいちいち覚えなくてもAIが答えてくれるでしょう。ですが、例えば「借りた覚えのないお金を返せという訴状が届いた。どう対応すべきか」という問題をAIに質問しても大した解答は得られません。せいぜい、訴状を読め、記憶をたどれ、弁護士に相談せよ、相手に確認せよ、といった回答が得られるだけです。これに正しく対応するためには、一定の法律知識または弁護士への丸投げが必要です。もう一つ例を挙げます。「食塩が水に溶ける現象を説明せよ」。AIの回答は、水に食塩を入れると食塩に水の分子が近づく、そもそも食塩はナトリウムイオンと塩化物イオンがイオン結合している・・・・(長くなるので省略します)。このAIの回答を理解するのには、「イオン」「イオン結合」「分子」などの理解が必要です。従って、AIが広まった現代でも依然として暗記は必要だと考えます。
< 結論 >
試験で要求される頭の良さの正体は、IQというよりも素早い計算力、素早い読解力、素早い暗記力です。それらは計算、読解、暗記を大量に実行することで培われます。つまり、「〇〇で上達したいのなら、たくさん〇〇するしかない」という至極当然な結論に至りました。
結論は平凡ですが、「もしかすると自分は勉強に向いていないのではないか」などと悩む必要はありません。教科のスコアを上げたいのであれば、どんどん理解して、理解したものをどんどん覚えたらよいのです。
暗記するときのもつべき心構えとしては、「覚えても次の日には半分以上忘れるのが当たり前だ」という認識をもつことです。「せっかく覚えたのに一週間後にはほとんど忘れてしまった。」と嘆くのは見当違いです。当たり前のことを嘆くのだから見当違いです。「お金を使ったらお金が減った」と嘆くようなものです。「今日せっかく英単語を100個覚えたのだから、記憶が消えないうちに明日も復習しなければならない」というマインドが大切です。この忘れることへの恐れをもつことで、頻繁な復習への意欲と、大量暗記のストックの維持が実現されます。忘れることへの恐れはやらされた勉強ではなく、自発的な勉強につながります。「人は欲か恐怖で動く」と言います。忘れることの恐れを抱くことで、自分を上手に動かして効果的に自分を高めることができるのです。
個別指導Up塾塾長 田中 俊成
2025年03月15日 14:38